アグロエコロジー
オランダの大学院で有機農業を勉強する留学生の日記
マルタ島のオーガニック農業
マルタ島でサイクリングしていると、石垣に囲まれた小さな畑が九十九折に重なっている景色を目にするだろう。
整地されていない不効率な畑がほとんどだ。
「マルタの町はオーガニックなんだ」
と、同じ宿に泊まっていたカナダ人のおばあちゃん。
まっすぐな道なんてない。すべてが入り組んでいて、わかりにくくて、効率が悪い。
でも、不効率なものに意味があることがわかるととても面白いのだ。
すべての道は有機的につながっている。まさにこの一見した不効率さは、オーガニックの原点なんじゃないだろうか。
積まれた石垣は、日本の竹富島に似ている気がする。マルタの石は石灰石が多い。
石垣に雨水をため、灌漑に使用されている畑もあった。
作物は、オリーブ、ハーブ、ぶどう、フルーツなどがごちゃまぜに植わっている。
神殿で所有しているというオーガニック農場の直売店を訪ねた。
EUの有機認証を取得している。

「マルタ島は戦時中食べ物がなく、ほとんど自給していた。農薬も化学肥料も使っていなかった。今もそのままでやってる。」
と、直売店で、昔ながらの編み物をしていたおばあちゃん。

店には、オーガニックのはちみつやジャムなどの加工品が並ぶ。
サボテンの実はバナナのようにむいて食べるのよ。というおばあちゃんの話につられ、サボテンの実ジャムを購入。
Tamarindに似ているのだけど、これをつぶして飲むと風邪のときにいいのだそう。
マルタ島の民間療法をいろいろと教えてくれた。

この島のオーガニックみかんはとてもおいしくて、試食したら買わずにはいられなかった。1パック(5こ)、1ユーロ。
いっきに2つ食べてしまった。みかん中毒になったのは初めてだ。
マルタの農地は家庭菜園規模に細分化されている。
入植者は畑つきの家を建てるのが慣例だったようで、入植者が増えるにつれ小さくなっていったという。
いまではマルタの主要産業は観光。オーナーは畑をやめて都市へ移動し、放置されている土地もあるとか。
黄色いお花畑が生い茂っているところがたくさんあった。
それもまたきれいなんだけど、今マルタは野菜を海外からの輸入に依存している。
こんなにも豊かな土地が残っているのに。
しかし、有機野菜の需要は高まっており、マルタ島でも昔ながらのオーガニック農業が見直されつつある。
「nature repairs itself」
マルタで活動するpermaculturaristは言う。
「厳しい環境で育ってきた在来の品種を使うことで、農薬や化学肥料に頼らなくても十分な生産が出来る。」
地産地消を基本とする有機農業の需要の高まりは、マルタの農業を後押しするかもしれない。
■マルタのパーマカルチャー
http://bahrijaoasis.blogspot.com/

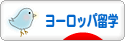
整地されていない不効率な畑がほとんどだ。
「マルタの町はオーガニックなんだ」
と、同じ宿に泊まっていたカナダ人のおばあちゃん。
まっすぐな道なんてない。すべてが入り組んでいて、わかりにくくて、効率が悪い。
でも、不効率なものに意味があることがわかるととても面白いのだ。
すべての道は有機的につながっている。まさにこの一見した不効率さは、オーガニックの原点なんじゃないだろうか。
積まれた石垣は、日本の竹富島に似ている気がする。マルタの石は石灰石が多い。
石垣に雨水をため、灌漑に使用されている畑もあった。
作物は、オリーブ、ハーブ、ぶどう、フルーツなどがごちゃまぜに植わっている。
神殿で所有しているというオーガニック農場の直売店を訪ねた。
EUの有機認証を取得している。
「マルタ島は戦時中食べ物がなく、ほとんど自給していた。農薬も化学肥料も使っていなかった。今もそのままでやってる。」
と、直売店で、昔ながらの編み物をしていたおばあちゃん。
店には、オーガニックのはちみつやジャムなどの加工品が並ぶ。
サボテンの実はバナナのようにむいて食べるのよ。というおばあちゃんの話につられ、サボテンの実ジャムを購入。
Tamarindに似ているのだけど、これをつぶして飲むと風邪のときにいいのだそう。
マルタ島の民間療法をいろいろと教えてくれた。
この島のオーガニックみかんはとてもおいしくて、試食したら買わずにはいられなかった。1パック(5こ)、1ユーロ。
いっきに2つ食べてしまった。みかん中毒になったのは初めてだ。
マルタの農地は家庭菜園規模に細分化されている。
入植者は畑つきの家を建てるのが慣例だったようで、入植者が増えるにつれ小さくなっていったという。
いまではマルタの主要産業は観光。オーナーは畑をやめて都市へ移動し、放置されている土地もあるとか。
黄色いお花畑が生い茂っているところがたくさんあった。
それもまたきれいなんだけど、今マルタは野菜を海外からの輸入に依存している。
こんなにも豊かな土地が残っているのに。
しかし、有機野菜の需要は高まっており、マルタ島でも昔ながらのオーガニック農業が見直されつつある。
「nature repairs itself」
マルタで活動するpermaculturaristは言う。
「厳しい環境で育ってきた在来の品種を使うことで、農薬や化学肥料に頼らなくても十分な生産が出来る。」
地産地消を基本とする有機農業の需要の高まりは、マルタの農業を後押しするかもしれない。
■マルタのパーマカルチャー
http://bahrijaoasis.blogspot.com/
PR
リンの枯渇が招く食料問題
湖の富栄養化を招くリン酸洗剤が問題となり、リン酸は環境によくないというイメージがあるが、植物にとっては窒素・カリウムと並んで重要な栄養素。
そして、原料は主に鉱石。石油と同じで、再生不可能資源なのだ。
リン鉱石の主な産地は中国。主要用途は科学肥料。
中国は貴重な鉱石の流出を防ぐため、高い関税をかけている。
日本ではあまりリン酸について騒がれていないが、こちらでは石油と並ぶ資源問題になっている。
オイルピークならず、「リン酸ピーク」といわれている。
食料の安全保障問題となるリンの枯渇。
イギリスのSoil Associationは、リン酸ピークは2033年くらいではないかという記事を紹介している。
リンがなくなれば、いままでの対症療法的なやり方では収量がおち、増え続ける人口を養えなくなる。
この問題の解決のためには有機農業を普及し、リンや資源の効率利用を図るべき。と、Soil Associationは提案している。
Soil Association website

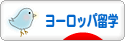
そして、原料は主に鉱石。石油と同じで、再生不可能資源なのだ。
リン鉱石の主な産地は中国。主要用途は科学肥料。
中国は貴重な鉱石の流出を防ぐため、高い関税をかけている。
日本ではあまりリン酸について騒がれていないが、こちらでは石油と並ぶ資源問題になっている。
オイルピークならず、「リン酸ピーク」といわれている。
食料の安全保障問題となるリンの枯渇。
イギリスのSoil Associationは、リン酸ピークは2033年くらいではないかという記事を紹介している。
リンがなくなれば、いままでの対症療法的なやり方では収量がおち、増え続ける人口を養えなくなる。
この問題の解決のためには有機農業を普及し、リンや資源の効率利用を図るべき。と、Soil Associationは提案している。
Soil Association website
地域で支える農業(CSA) 2
以前紹介したCSA( Community Supported Agriculture )ファームのオーナーさんが講義に来てくれました。
彼の農場で作られた野菜は、直売所で売るでもなく、自分の店で売るでもなく、すべて、会員が自分で好きなだけ収穫してもって帰る。
収穫やパッケージング、輸送の手間が省けるのだ。
会員になれば好きなだけ収穫できるオーガニック農場
De Nieuwe Ronde
http://agroecology.blog.shinobi.jp/Entry/65/
すべての売上、コスト、労働者の給料、オーナーの取り分まですべて会員に公開している。
CSAの会員になれば、自動的にコンシューマーグループの会員になる。
コンシューマーグループとオーナーが契約を結び、オーナーは消費者に代わって野菜を育てる労働者という位置づけなのだそうだ。
何を植えるか、値段はいくらにするか、コンシューマーグループの総会で意思決定を図る。
オーナーは技術的なアドバイスを行う。
いわば、会員は共同経営者なのだ。
収穫し放題のため、会員は一定人数に制限している。
責任を持って農場経営にかかわれる人数に限りがあるという理由もある。
会費は年間約2万円。
それでも、このシステムでは一人でいっぱい採っていく人はいない。
会員一人ひとりが、他の会員の行動を監視しているのだ。
それどころか、コンシューマーグループの方から、オーナーの収入が低すぎるからという理由で会費の値上げを自ら決定したという。
日本でも棚田オーナー制やワインオーナー制など、似たようなシステムがあるが、ここまで厳密にやっているところはあまりないだろう。
とても面白い例だ。
また遊びに行こう。


彼の農場で作られた野菜は、直売所で売るでもなく、自分の店で売るでもなく、すべて、会員が自分で好きなだけ収穫してもって帰る。
収穫やパッケージング、輸送の手間が省けるのだ。
会員になれば好きなだけ収穫できるオーガニック農場
De Nieuwe Ronde
http://agroecology.blog.shinobi.jp/Entry/65/
- オープン・ブッキング
- 共同意思決定
すべての売上、コスト、労働者の給料、オーナーの取り分まですべて会員に公開している。
CSAの会員になれば、自動的にコンシューマーグループの会員になる。
コンシューマーグループとオーナーが契約を結び、オーナーは消費者に代わって野菜を育てる労働者という位置づけなのだそうだ。
何を植えるか、値段はいくらにするか、コンシューマーグループの総会で意思決定を図る。
オーナーは技術的なアドバイスを行う。
いわば、会員は共同経営者なのだ。
収穫し放題のため、会員は一定人数に制限している。
責任を持って農場経営にかかわれる人数に限りがあるという理由もある。
会費は年間約2万円。
それでも、このシステムでは一人でいっぱい採っていく人はいない。
会員一人ひとりが、他の会員の行動を監視しているのだ。
それどころか、コンシューマーグループの方から、オーナーの収入が低すぎるからという理由で会費の値上げを自ら決定したという。
日本でも棚田オーナー制やワインオーナー制など、似たようなシステムがあるが、ここまで厳密にやっているところはあまりないだろう。
とても面白い例だ。
また遊びに行こう。
オーガニックヤギ牧場
Amsterdam bosにあるヤギ牧場に行ってきました。
この市民牧場では、鳥、ヤギ、牛、豚を一緒に飼っている。
ヤギの周りを鶏が飛び回り、ヤギは豚になついている。
異種類の動物同士の交流がとっても面白いです。
↓ヤギが豚にちょっかいだしてる様子
あとで、アニマルやってるコリドーメイトに聞くと、この手の「エコ・テクノロジー」では、むしろ日本が有名なんだそう。
なんとなく、むつごろうさんを思い出しました。
日本の牧場も探検してみたいです。
Goat Farm "The Ridammerhoeve"
http://www.geitenboerderij.nl/


この市民牧場では、鳥、ヤギ、牛、豚を一緒に飼っている。
ヤギの周りを鶏が飛び回り、ヤギは豚になついている。
異種類の動物同士の交流がとっても面白いです。
↓ヤギが豚にちょっかいだしてる様子
あとで、アニマルやってるコリドーメイトに聞くと、この手の「エコ・テクノロジー」では、むしろ日本が有名なんだそう。
なんとなく、むつごろうさんを思い出しました。
日本の牧場も探検してみたいです。
Goat Farm "The Ridammerhoeve"
http://www.geitenboerderij.nl/
オーガニック・グリーンハウス
ロッテルダムの近くにあるオーガニックのグリーンハウスを見学してきました。
10年前にオーガニックに転換したというフランク。
スペイン産の安いトマトと差別化するために、wild wonderというプロジェクトを始め、7haの温室には、
7種類の胡椒と20種類のトマトを栽培されています。

■病害虫管理
オーガニックで大変なのは病害虫管理。一度病気が広まってしまえば、農薬を使うことができないので被害が大きくなり、ひどい時には作物の50%がだめになってしまうそう。
フランクは、月に1回の土壌診断に加え、年に1度、生物多様性診断を行っています。
どれだけの有用微生物がどのくらいいるかを見て、バランスを図っているのです。
トマトの主な害虫であるセンチュウは、胡椒にはあまりつかない。
区画をトマトと胡椒に分け、ローテーションを行いながらセンチュウが増えないように調整。
このプロセスで、有機に変えてから2年目には8000/m2いたセンチュウが、次の年には1,000/m2に減ったのだとか。
センチュウの数を数えてるところがすごいです・・・。


▲wild wonder
■収穫
トマトの熟れ具合は種類によって違うので、収穫のタイミング管理が大事。
中には収穫後に破裂しやすい種類は、とくに輸出向けだと熟すけっこう前に収穫。
やっぱり地元産が一番ですね!
(ちなみに写真の黄色いのは、品種の違いで、すでに熟している)
■流通
しかし、驚きなのは、この温室で作られているトマトと胡椒の約10%が国内流通向けで残りはアメリカ、カナダ、フランス、ドイツに輸出されるのだという。
グリーンハウスの盛んなオランダでは競争率が激しく、プレミア価格がつきにくいのだとか。
ここの温室は「ヨスタ」というオーガニック専門のマーケティング会社と契約し、販売戦略をたてています。
これまでは、ヨスタは国内市場にあまり興味がなく、商品の半分をアメリカに輸出されていましたが、最近では、国内や近隣諸国にシフトする方向に変わってきているそうです。
有機野菜の輸出価格は、トマトは慣行農法の50%増、胡椒は70%増(1.7倍)になるそうです。
フランクが有機農業を始めたころは、商品の80%がオーガニック専門店で、スーパーに卸すのは20%程度でしたが、今や、80%がスーパー、20%が有機専門店にわたっています。
スーパーの意識がオーガニックに向いてきているようです。
■ホームページ
http://www.natureandmore.com/growers/frank-de-koning


10年前にオーガニックに転換したというフランク。
スペイン産の安いトマトと差別化するために、wild wonderというプロジェクトを始め、7haの温室には、
7種類の胡椒と20種類のトマトを栽培されています。
■病害虫管理
オーガニックで大変なのは病害虫管理。一度病気が広まってしまえば、農薬を使うことができないので被害が大きくなり、ひどい時には作物の50%がだめになってしまうそう。
フランクは、月に1回の土壌診断に加え、年に1度、生物多様性診断を行っています。
どれだけの有用微生物がどのくらいいるかを見て、バランスを図っているのです。
トマトの主な害虫であるセンチュウは、胡椒にはあまりつかない。
区画をトマトと胡椒に分け、ローテーションを行いながらセンチュウが増えないように調整。
このプロセスで、有機に変えてから2年目には8000/m2いたセンチュウが、次の年には1,000/m2に減ったのだとか。
センチュウの数を数えてるところがすごいです・・・。
▲wild wonder
■収穫
トマトの熟れ具合は種類によって違うので、収穫のタイミング管理が大事。
中には収穫後に破裂しやすい種類は、とくに輸出向けだと熟すけっこう前に収穫。
やっぱり地元産が一番ですね!
(ちなみに写真の黄色いのは、品種の違いで、すでに熟している)
■流通
しかし、驚きなのは、この温室で作られているトマトと胡椒の約10%が国内流通向けで残りはアメリカ、カナダ、フランス、ドイツに輸出されるのだという。
グリーンハウスの盛んなオランダでは競争率が激しく、プレミア価格がつきにくいのだとか。
ここの温室は「ヨスタ」というオーガニック専門のマーケティング会社と契約し、販売戦略をたてています。
これまでは、ヨスタは国内市場にあまり興味がなく、商品の半分をアメリカに輸出されていましたが、最近では、国内や近隣諸国にシフトする方向に変わってきているそうです。
有機野菜の輸出価格は、トマトは慣行農法の50%増、胡椒は70%増(1.7倍)になるそうです。
フランクが有機農業を始めたころは、商品の80%がオーガニック専門店で、スーパーに卸すのは20%程度でしたが、今や、80%がスーパー、20%が有機専門店にわたっています。
スーパーの意識がオーガニックに向いてきているようです。
■ホームページ
http://www.natureandmore.com/growers/frank-de-koning
羊の調教
有機農業では農薬が使えないので、雑草対策に様々な対策が講じられていますが、雑草対策に羊をトレーニングして使うという取り組みが行われているようです。
休耕地対策のために、家畜を放牧している例はよく聞きますが、こちらでは作物が育っているときに中耕除草として羊を放しているのが面白いです。
羊は、作物まで食べてしまうのですが、調教することによって食べていい雑草を覚えるのだそうです。
毛皮にもなり、労働力にもなり、最後は肉になり(涙)。
羊さんは働き者です
http://news.ucanr.org/newsstorymain.cfm?story=977


休耕地対策のために、家畜を放牧している例はよく聞きますが、こちらでは作物が育っているときに中耕除草として羊を放しているのが面白いです。
羊は、作物まで食べてしまうのですが、調教することによって食べていい雑草を覚えるのだそうです。
毛皮にもなり、労働力にもなり、最後は肉になり(涙)。
羊さんは働き者です
http://news.ucanr.org/newsstorymain.cfm?story=977
世界最大のオーガニック見本市Bio Fach 2010 in ニュルンベルク(4)
日本からの講演者は誰もいなかったので、日本でビジネスを行っているドイツの企業が日本のオーガニック市場についてプレゼンを行いました。
言われたい放題です・・・^^;
要 旨


言われたい放題です・・・^^;
要 旨
- 日本政府は、早々とオーガニックに関する法律を整えたことは評価できる。
- しかし、市民の認識が追い付いていない。運用に問題がある。
- 日本のオーガニック市場は未熟だが徐々に伸びている。忍耐が必要。
- 流通システムがとても複雑で、小売価格が高めである。
- 自然食品、ナチュラル、無添加などの言葉が氾濫している。違いが不明確。
- 認証を受けているのは外国製品が多い(輸入主導型)
- 食品安全が重要(環境問題、アニマルウェルフェアなどと比べて)
- オーガニックのシェアは低い。
- 生協がスーパーよりも大きなカギを握っている。(産直・TEIKEI)
- 必ずしも有機認証はとっていないが、日本では信頼で成り立つ顔の見える取引が盛ん。
- 日本のマーケット参入には信頼のおけるプロフェッショナル・パートナーが欠かせない。
- IFOAMの集会が次回韓国で開催される。
世界最大のオーガニック見本市Bio Fach 2010 in ニュルンベルク(3)
中国の有機農業事情
中国政府によるオーガニックマーケットについての発表がありました。
現在、中国でも有機食品の需要が増えています。
日本での有機認証は民間企業がおこなっているのに対し、中国の有機認証は政府関連機関が行っています(民間の認証団体もありますが)。
つまり、政府が認証を後押ししているのです。
2009年には、1000社を超える企業が有機認証を取得、4755の商品が認証されています。
目的は、国内市場への有機食品プロモーションもありますが、日本などの市場へのオーガニック食品輸出のためです。
中国のオーガニック商品は、国内だけでなく国際市場にとっても今後シェアを伸ばしていくと考えられます。
認証ロゴ

現在のところ、JASやBIOなどの外国の認証制度との互換性がなく、中国市場でオーガニック食品を販売したい場合は、別途中国の認証を受ける必要があるようだ。
都市部を中心にLOHASブームが盛んだという中国。
日本を超えるオーガニック市場ができるかもしれません。


全体の農産物に占めるオーガニックの割合はまだまだ低いものの、
面積でいえば、中国は世界第5位の有機農産物生産国なのだ。
中国のオーガニック制度は始まったばかり。
制度では日本がリードしているが、運用面では世界から遅れをとっている。
オーガニック界の第2の黒船は、中国かもしれない。


中国政府によるオーガニックマーケットについての発表がありました。
現在、中国でも有機食品の需要が増えています。
日本での有機認証は民間企業がおこなっているのに対し、中国の有機認証は政府関連機関が行っています(民間の認証団体もありますが)。
つまり、政府が認証を後押ししているのです。
2009年には、1000社を超える企業が有機認証を取得、4755の商品が認証されています。
目的は、国内市場への有機食品プロモーションもありますが、日本などの市場へのオーガニック食品輸出のためです。
中国のオーガニック商品は、国内だけでなく国際市場にとっても今後シェアを伸ばしていくと考えられます。
認証ロゴ
- 国家認証ロゴ 2つ
- 有機認証団体 2つ
- 外国の認証団体 4つ
- ベーシックレベル:環境に優しい食品
- グリーンフードラベル:減農栽培
- オーガニック
現在のところ、JASやBIOなどの外国の認証制度との互換性がなく、中国市場でオーガニック食品を販売したい場合は、別途中国の認証を受ける必要があるようだ。
都市部を中心にLOHASブームが盛んだという中国。
日本を超えるオーガニック市場ができるかもしれません。
全体の農産物に占めるオーガニックの割合はまだまだ低いものの、
面積でいえば、中国は世界第5位の有機農産物生産国なのだ。
中国のオーガニック制度は始まったばかり。
制度では日本がリードしているが、運用面では世界から遅れをとっている。
オーガニック界の第2の黒船は、中国かもしれない。
世界最大のオーガニック見本市Bio Fach 2010 in ニュルンベルク(2)
bio fach ビオ・バッハでは展示だけでなく、各団体のレクチャーや、シンポジウムが開催されており、自由に参加することができます。
初日は約60のレクチャープログラムがありました。
私の授業でのテーマは、NGOとオーガニックだったので、NGOが開催しているプログラムに参加しました。
Hotspot for biodiversity
品質管理や認証を行っているIMO(institute for Marketecology)とFair Wildが中心になって進めている自然資源管理プロジェクトのプレゼンでした。
とても面白かったので紹介します。
オーガニック認証を受けた商品であっても、必ずしも品質が保証されているものではありません。労働状況が監査の対象になることはありません。
プロセスのみの基準なので、きめられた手順を守っていれば、生態系の変化や社会への影響などの「結果」が問われることはありません。
オーガニックは高く売れるからと、大企業が開発にのりだし、途上国で搾取をおこなっていたとしても「環境に優しいオーガニック」なわけです。
そうなると、オーガニックは慣行化(conventionalise)してしまいます。
そこで新しい基準を用い、社会や品質、生態系の管理を同時に見ていこうという動きが生まれています。
オーガニック+フェアトレードの概念です。
パートナー
www.fairwild.org/

初日は約60のレクチャープログラムがありました。
私の授業でのテーマは、NGOとオーガニックだったので、NGOが開催しているプログラムに参加しました。
Hotspot for biodiversity
品質管理や認証を行っているIMO(institute for Marketecology)とFair Wildが中心になって進めている自然資源管理プロジェクトのプレゼンでした。
とても面白かったので紹介します。
このプロジェクトでは、自然の産物をwild collected productsとして認証を行っているのですが、生産過程だけでなくいろんな指標を使っています。
- Ecological(環境面)
- Social(社会面)
- Quality(品質)
- Health and safety(健康と安全)
オーガニック認証を受けた商品であっても、必ずしも品質が保証されているものではありません。労働状況が監査の対象になることはありません。
プロセスのみの基準なので、きめられた手順を守っていれば、生態系の変化や社会への影響などの「結果」が問われることはありません。
オーガニックは高く売れるからと、大企業が開発にのりだし、途上国で搾取をおこなっていたとしても「環境に優しいオーガニック」なわけです。
そうなると、オーガニックは慣行化(conventionalise)してしまいます。
そこで新しい基準を用い、社会や品質、生態系の管理を同時に見ていこうという動きが生まれています。
オーガニック+フェアトレードの概念です。
パートナー
- SIPPO
- IUCN
- Medicinal plant specialist group
- IMO
- Traditional medicinal
- WWF
- カザフスタン
- ウズベキスタン
- ネパール
- 中国
- ボスニア
- アルバニア
www.fairwild.org/
世界最大のオーガニック見本市Bio Fach 2010 in ニュルンベルク(1)
バスで往復16時間。
ニュルンベルクで開催されていた世界一のオーガニック大会、bio fachに参加してきました。
このイベントは、必修科目なので、クラスメート全員が参加。
この年になって修学旅行みたいなことするとは思わなかった。
枕投げしたり。
雪合戦したり。
楽しかった。
ただ・・
テスト前でなければ最高だったのに。
みんな教科書持参。宿で勉強。
せっかくの南ドイツ、結局国際会議場しか見れなかった。
夕食も宿でパンとか、カップめんとか・・・。
高校の時の勉強合宿おもいだす。
アフリカ、アラビア、南米、アジア各国からの参加企業・団体は2000以上。
かなりの広さで、1日ではまわりきれません。
▼入場ゲート
日本の同様のイベントでは、ファミリー客が冷やかしにきている感じでしたが、こちらの大会は、完全に商業ベース。
会場で売買することはできず展示のみなので、ファミリー客の姿はなく、かわりにビジネスマンやメディア、研究者の来客がほとんどです。
▼IFOAMカフェ
日本から来ていたのは5つの団体。
こちらは石川県の企業のブース。
お寿司があったので、クラスメートに教えてあげたら喜んでいたけど、お寿司メインじゃなく、お醤油の展示がメインだったみたい・・・。
NGO、国際支援団体、オーガニック研究所、有機認証団体、政府関係団体、など、世界中から数え切れないほどの出展があり、インターンシップ先を探すには絶好の機会でした。
ブースめぐりをしながら、いくつか連絡先を入手してきました。
やりたいことがたくさんあって、どこで働こうか今からとても楽しみです。
プロフィール
ブログ移動しました
「アグロエコロジー」続編:
http://agro-ecology.blogspot.jp/
たねのもりびと
ワーゲニンゲン大学大学院
有機農業研究科修了
(アグロエコロジー専攻)
Wageningen University
MSc of Organic Agriculture
ブータン政府GNH委員会インターン
国を100%オーガニックにする国家プロジェクトに従事
■ご挨拶
ご挨拶
■連絡先
メールフォーム
当サイトはリンクフリーです。

「アグロエコロジー」続編:
http://agro-ecology.blogspot.jp/
たねのもりびと
ワーゲニンゲン大学大学院
有機農業研究科修了
(アグロエコロジー専攻)
Wageningen University
MSc of Organic Agriculture
ブータン政府GNH委員会インターン
国を100%オーガニックにする国家プロジェクトに従事
■ご挨拶
ご挨拶
■連絡先
メールフォーム
当サイトはリンクフリーです。

