アグロエコロジー
オランダの大学院で有機農業を勉強する留学生の日記
ブータン人の慈悲心
Dewathangの町に有名なヤギがいる。
おてんばなラバ(ヤギ)君は、子供が木のブランコにのっているのをみて、ブランコにチャレンジ。
店の商品を食べてみたり、子供に突進したり。

ラバ君は、本来インドに売られ、肉となって帰ってくる予定だった。
ブータンには食肉加工所がないため、農家は家畜をインドに売り渡す。
Tashi Yantseから連れてこられたラバ君の命を救うため、Samdrup Jongkharの商人が買い取った。
以来、ラバ君はDewathangの商人に見守られながら、自由に暮らしている。
敬虔な仏教徒であるブータン人は、生き物をお金儲けに使うことを罪だと考える。
「所得向上のために養鶏所や養豚所の設置を進めても、ブータンではうまくいかない。」
と、家畜保健所のスタッフは言う。
鶏は、みみずや生き物を食べる。大量に飼えば儲かるかもしれないが、たくさんの命を奪ってまでやろうと思わない、と農家は乗り気ではないのだ。
ラバ君を見ていると、ブータン人の慈悲心の象徴のような気がしてくる。
やんちゃな姿がほほえましく思えるのだった。
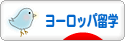

おてんばなラバ(ヤギ)君は、子供が木のブランコにのっているのをみて、ブランコにチャレンジ。
店の商品を食べてみたり、子供に突進したり。
ラバ君は、本来インドに売られ、肉となって帰ってくる予定だった。
ブータンには食肉加工所がないため、農家は家畜をインドに売り渡す。
Tashi Yantseから連れてこられたラバ君の命を救うため、Samdrup Jongkharの商人が買い取った。
以来、ラバ君はDewathangの商人に見守られながら、自由に暮らしている。
敬虔な仏教徒であるブータン人は、生き物をお金儲けに使うことを罪だと考える。
「所得向上のために養鶏所や養豚所の設置を進めても、ブータンではうまくいかない。」
と、家畜保健所のスタッフは言う。
鶏は、みみずや生き物を食べる。大量に飼えば儲かるかもしれないが、たくさんの命を奪ってまでやろうと思わない、と農家は乗り気ではないのだ。
ラバ君を見ていると、ブータン人の慈悲心の象徴のような気がしてくる。
やんちゃな姿がほほえましく思えるのだった。
PR
英語スピーチコンテストに飛び入り参加
今日は私が滞在しているエンジニアリング専門学校で英語のスピーチコンテストがあった。
たまたま、知り合いの先生に会いに行ったら審査員として参加していたので、私も見学させてもらうことに。
ブータン人は小学校から物理や歴史などほとんどの授業を英語で受けているので、そこらへんの英語公用語国よりも英語ができる学生が多い。
国語のゾンカよりも、英語の小説の方が簡単に読めるというから驚きだ。
友人によると、もちろん彼女へ送るポエムも、ゾンカでなく英語で書くらしい。
私が会場に入ったころにはすでに終盤だった。
一通りのスピーチが終えた後、審査員による採点の集計のために、司会者が飛び入りスピーチを募集した。2,3人の立候補が両親への感謝について、読書のすすめ、などのテーマで語った。
ボランティアはすべて男子学生で、司会者は女子生徒で誰かスピーチしたい人はいないか?と声をかけるが誰も現れない。
知り合いの先生はまだ集計が終わらないので、君、ちょっと何かしゃべってきてよ、という。
会場には約100人-200人ほどの生徒。
これは自分の活動について売り込むチャンス!
これが何かのきっかけにむすびつくかもしれない。
面白そうなので、やってみようと思った。
即興スピーチ、テーマは「ブータンのGNHについて感じたこと」
ブータンと日本の違いは何か?
これ、よく聞かれる質問。
なんでしょう?
まず、1つめに、大きなお腹。
ブータン人は、よく食べる。
日本人は、少量のご飯と、野菜をいっぱいたべる。
ブータンは正反対だ。少量の野菜に、大量の米を食べる。
だから、お腹が大きくなる。
お腹の大きさははGNHの指標である。
いっぱいたべればGNHは向上する。
2つめに、ブータン人はsocial relationshipを大事にすることだ。
ブータン人は、よく飲む。
農家はみんな一緒に働く。みんなで草取りをし、みんなで休憩し、みんなで飲む。
農作業が終われば、家に帰ってやっぱり集まってみんなで飲む。
日本では、こういう近所付き合いがなくなってきている。
social relationもまたGNHの指標だと思う。
よく食べ、よく飲み、人との関わりを大事にする。これがHappinessにつながっている。
そんな良い文化を日本にもって帰りたいと思う。
lastly、I would not mind if some of you can visit me with Ara, Banchan.
最後に、アラ、バンチャン(地酒)持って私の家に来てもらっても全然かまわないわよ ;)
と言ったら、一同大爆笑。つかみはOK?
けど、以来、知らない人から指さされて笑われることがあるのが悩みの種だ。
一躍有名人になってしまった。
(まじで、酒もってこられたりするし・・)
ブータンでの世話役のCheku君から、
「また、君はやってくれるね。」
といわれてしまった^^;。
「ブータンの田舎は狭い社会だから、いい噂も悪い噂も尾ひれはひれ付けて広まる。目立たず、騒がず、じっとしてろ」、と彼は日ごろからよく言う。
私の歯に衣を着せない言動にひやひやしているようだった。
ブータンに来て1カ月。なんとなく、彼の懸念を実感してきたところだ。
気をつけなければ・・・。
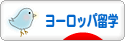

たまたま、知り合いの先生に会いに行ったら審査員として参加していたので、私も見学させてもらうことに。
ブータン人は小学校から物理や歴史などほとんどの授業を英語で受けているので、そこらへんの英語公用語国よりも英語ができる学生が多い。
国語のゾンカよりも、英語の小説の方が簡単に読めるというから驚きだ。
友人によると、もちろん彼女へ送るポエムも、ゾンカでなく英語で書くらしい。
私が会場に入ったころにはすでに終盤だった。
一通りのスピーチが終えた後、審査員による採点の集計のために、司会者が飛び入りスピーチを募集した。2,3人の立候補が両親への感謝について、読書のすすめ、などのテーマで語った。
ボランティアはすべて男子学生で、司会者は女子生徒で誰かスピーチしたい人はいないか?と声をかけるが誰も現れない。
知り合いの先生はまだ集計が終わらないので、君、ちょっと何かしゃべってきてよ、という。
会場には約100人-200人ほどの生徒。
これは自分の活動について売り込むチャンス!
これが何かのきっかけにむすびつくかもしれない。
面白そうなので、やってみようと思った。
即興スピーチ、テーマは「ブータンのGNHについて感じたこと」
ブータンと日本の違いは何か?
これ、よく聞かれる質問。
なんでしょう?
まず、1つめに、大きなお腹。
ブータン人は、よく食べる。
日本人は、少量のご飯と、野菜をいっぱいたべる。
ブータンは正反対だ。少量の野菜に、大量の米を食べる。
だから、お腹が大きくなる。
お腹の大きさははGNHの指標である。
いっぱいたべればGNHは向上する。
2つめに、ブータン人はsocial relationshipを大事にすることだ。
ブータン人は、よく飲む。
農家はみんな一緒に働く。みんなで草取りをし、みんなで休憩し、みんなで飲む。
農作業が終われば、家に帰ってやっぱり集まってみんなで飲む。
日本では、こういう近所付き合いがなくなってきている。
social relationもまたGNHの指標だと思う。
よく食べ、よく飲み、人との関わりを大事にする。これがHappinessにつながっている。
そんな良い文化を日本にもって帰りたいと思う。
lastly、I would not mind if some of you can visit me with Ara, Banchan.
最後に、アラ、バンチャン(地酒)持って私の家に来てもらっても全然かまわないわよ ;)
と言ったら、一同大爆笑。つかみはOK?
けど、以来、知らない人から指さされて笑われることがあるのが悩みの種だ。
一躍有名人になってしまった。
(まじで、酒もってこられたりするし・・)
ブータンでの世話役のCheku君から、
「また、君はやってくれるね。」
といわれてしまった^^;。
「ブータンの田舎は狭い社会だから、いい噂も悪い噂も尾ひれはひれ付けて広まる。目立たず、騒がず、じっとしてろ」、と彼は日ごろからよく言う。
私の歯に衣を着せない言動にひやひやしているようだった。
ブータンに来て1カ月。なんとなく、彼の懸念を実感してきたところだ。
気をつけなければ・・・。
養鶏所でのチキンレース
今日は獣医が鶏のワクチン接種にReckhey村に行くというので連れて行ってもらった。
ブータンで初のバイク2人乗り。でこぼこの道をはねながら進むこと30分のところに養鶏所があった。
オーナーのWondaさんは、インドで獣医師免許を取得した後、実家の小売店を継ぎ、卵を実家の店で直販するために養鶏所を開設した。
彼が飼っているインドからの外来種であるRed eyeは、1年に約230個の卵を産む。ローカル種の60-70個に比べるとずいぶん生産性が高い。
2か月前に家畜保健所から510羽のヒナを購入したばかりだという。
そしてこの外来種は1羽あたり38ニュルタムで手に入れることができるので、500匹買っても2000ニュルタム(約4000円)の投資だ。
卵1個あたり10ニュルタムで販売されている。つまり、売り上げは1年で230x500x10=1,150,000(約200万円)になる。卵の生産は17、18週目から72週目までだという。十分な知識さえあればかなりおいしいビジネスだろう。
しかし、Red eye の難しいところは、生産性が高いかわりに、管理が難しいところにある。
500匹同時に買えば、熱中症にかかりやすくなる。Wondaの養鶏所ではすでに約30匹死亡した。
New Castle diseaseを防ぐために、2週間に1度はワクチンを接種しないといけないという。
「500匹の鶏にワクチンを打ちにいく」という話を聞いて、ぜひ見てみたくなった。
助手として連れて行ってもらうことに。
まず、鳥小屋を2つに区切る。接種済みの鶏を1方に移していくのだ。
これがなかなか大変!
鶏のヒナはすごくすばしっこく、やっとのことで角に追い込んでもひっかきまわされ、じたばた飛び回る。まったく落ち着きがない、、、
どこかで聞いた話だなぁと思ったら、
「酉年生まれは落ち着きがない。いつも飛び回っている。」(byブータンの占星術師)
うーん、それは私のことか?!
てなことを考えながら、鶏と追いかけっこを楽しむこと2時間。
すっかり鶏2羽同時キャッチできるようになり、chicken masterの称号をいただく。
ちなみに、chicken doctorは3羽同時キャッチ、最大4羽同時キャッチできるから驚きだ。

やっとのことで470匹のワクチン接種完了。
とてもよい経験だったけど、この作業を2週間に1度するのか、と思うとちょっとうんざりするかもしれない・・・。
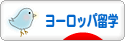

ブータンで初のバイク2人乗り。でこぼこの道をはねながら進むこと30分のところに養鶏所があった。
オーナーのWondaさんは、インドで獣医師免許を取得した後、実家の小売店を継ぎ、卵を実家の店で直販するために養鶏所を開設した。
彼が飼っているインドからの外来種であるRed eyeは、1年に約230個の卵を産む。ローカル種の60-70個に比べるとずいぶん生産性が高い。
2か月前に家畜保健所から510羽のヒナを購入したばかりだという。
そしてこの外来種は1羽あたり38ニュルタムで手に入れることができるので、500匹買っても2000ニュルタム(約4000円)の投資だ。
卵1個あたり10ニュルタムで販売されている。つまり、売り上げは1年で230x500x10=1,150,000(約200万円)になる。卵の生産は17、18週目から72週目までだという。十分な知識さえあればかなりおいしいビジネスだろう。
しかし、Red eye の難しいところは、生産性が高いかわりに、管理が難しいところにある。
500匹同時に買えば、熱中症にかかりやすくなる。Wondaの養鶏所ではすでに約30匹死亡した。
New Castle diseaseを防ぐために、2週間に1度はワクチンを接種しないといけないという。
「500匹の鶏にワクチンを打ちにいく」という話を聞いて、ぜひ見てみたくなった。
助手として連れて行ってもらうことに。
まず、鳥小屋を2つに区切る。接種済みの鶏を1方に移していくのだ。
これがなかなか大変!
鶏のヒナはすごくすばしっこく、やっとのことで角に追い込んでもひっかきまわされ、じたばた飛び回る。まったく落ち着きがない、、、
どこかで聞いた話だなぁと思ったら、
「酉年生まれは落ち着きがない。いつも飛び回っている。」(byブータンの占星術師)
うーん、それは私のことか?!
てなことを考えながら、鶏と追いかけっこを楽しむこと2時間。
すっかり鶏2羽同時キャッチできるようになり、chicken masterの称号をいただく。
ちなみに、chicken doctorは3羽同時キャッチ、最大4羽同時キャッチできるから驚きだ。
やっとのことで470匹のワクチン接種完了。
とてもよい経験だったけど、この作業を2週間に1度するのか、と思うとちょっとうんざりするかもしれない・・・。
ブータンでの生活
気づいたらもう5月。ブータンに来てから1カ月がたった。
昨日から学生寮からアパートに引っ越しし、引っ越しパーティーをした。
来週にはカナダ人のルームメイトがやってくる予定。
この間、今までにないくらいのんびりした生活をしている。
お祭りを見に行ったり、お寺に参拝にいったり。
マーケットに行くだけで1日の予定が終わってしまったり・・・


思うようにスケジュールが進まずいらいらすることもあった。
でも、こんなにいろんなことを考えさせられることがあったろうか。
寺の坊主に進められ、瞑想を始めた。
先週は、最寄りの車道から山道を歩くこと1時間の村を2往復した。
村落調査のすばらしいところは、村に行くたびにご飯と地酒が出てくることだ。

タクシー代の予算がおりたので来週からはタイトなスケジュールになる予定。
2名のカナダ人研究者と合流し、4つの地区を回る。
のんびり生活に飽きてきたので新生活ちょっと楽しみだ。
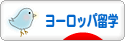

昨日から学生寮からアパートに引っ越しし、引っ越しパーティーをした。
来週にはカナダ人のルームメイトがやってくる予定。
この間、今までにないくらいのんびりした生活をしている。
お祭りを見に行ったり、お寺に参拝にいったり。
マーケットに行くだけで1日の予定が終わってしまったり・・・
思うようにスケジュールが進まずいらいらすることもあった。
でも、こんなにいろんなことを考えさせられることがあったろうか。
寺の坊主に進められ、瞑想を始めた。
先週は、最寄りの車道から山道を歩くこと1時間の村を2往復した。
村落調査のすばらしいところは、村に行くたびにご飯と地酒が出てくることだ。
タクシー代の予算がおりたので来週からはタイトなスケジュールになる予定。
2名のカナダ人研究者と合流し、4つの地区を回る。
のんびり生活に飽きてきたので新生活ちょっと楽しみだ。
Teacher's Day
小学校の先生が今日は「教師の日」で子供たちがイベントを企画しているので見に来ないかというお誘いがあった。
普段はハーフキラを来ている子たちも今日は、フルキラで登場。
ダンスやファッションショーなどで楽しませてくれた。


ランチも生徒たちが準備し、先生をもてなす。
たまにはこんな日もいいものだ、と先生たち。
日本にも先生の日があれば、先生大喜びかもしれない。
普段はハーフキラを来ている子たちも今日は、フルキラで登場。
ダンスやファッションショーなどで楽しませてくれた。
ランチも生徒たちが準備し、先生をもてなす。
たまにはこんな日もいいものだ、と先生たち。
日本にも先生の日があれば、先生大喜びかもしれない。
有機農業とGNH
「国の発展はGDPでなくGHN(Gross National Happiness)で測るべきである」
と、提唱したのはブータン国王。
私はブータンではGNH Comissionという機関のコンサルタントという位置付けになっている。
ブータン南部のこの町は外国人が珍しいので(私を含め、現在2人だけ)、よく話しかけられる。
もっとも、ほとんどの人は私をブータン人だと思っているので外国人だというと驚かれるのだけど。
GNHのコンサルタントって何するの?と聞かれることが多々ある。
私の専門は有機農業なので、有機農業は国民のGNHにどう影響するか?もし有機農業でGNHが悪くなるとすれば、どうすれば改善できるのか?というテーマで現状調査をしている。
ブータン政府は2020年までにブータン全土をオーガニックの国にするという至高の目標を掲げている。
ブログ読者からのメールの中には次のようなコメントがあった。
・ブータンって、閉鎖社会でもともと持続的なオーガニックなのでは?
・農薬や化学肥料は輸入しなくてはいけないので裕福な農家しか買えないのでは?
実は低いブータンの食糧自給率
ブータンは、経済のほとんどを海外に依存している。
税金収入は国家収益の1/3。残りは、海外からの援助(おもにインド)と水力発電で賄っている。
コメの自給率は50%。日本より低いのだ。
マーケットに売られている野菜はほとんどがインド産。
地元産は、収穫の季節に自分たちが食べる以上に採れた時のみ売られるため、不定期で価格変動が激しい。
地元産が食べたくなったら農家から直接買うか分けてもらわないといけない。
ブータン人の政府依存体質
ブータン人は、野菜の種や果樹の苗の配給、家畜の医療費、子供の教育まですべて政府に依存している。
農業普及員と村周りしていると、次はこの種がほしい、殺虫剤がほしいとおねだりに出くわす。
自分で買う必要がないので(化学肥料と殺虫剤は低額で配給)、インド人農家のようにわざわざ品種改良に自ら投資したり、雨水集積のための努力をすることはあまりない。
農業普及員はいう。
「農家は有機農業でもっとお金を儲けるためにマーケティングを政府にお願いしてくるのだけど、収量を上げるとか、品質を良くするとか、マーケティング以前に取り組まないといけない努力をせずに結果だけ求めるので困っている。」
ブータン人の海外依存と政府依存は簡単に変えられない困った問題だと思う。
借金漬けになって自殺する農家が後をたたないインドとは違って、土地を含め必要物資はほとんど無料で供給されるブータンはかなり幸せなことだろう。
しかし、農家の自助努力を促す取り組みが必要なのではないだろうか。
農家の自立を促す取り組み
種を大量生産しているのはDruk Seedのみであり、毎年政府が農家からの要望を取りまとめ、Druk Seedに依頼し、各農家に格安で配布されている。
新しい品種などはプロモーションのため無料で配られるため、マーケットに売りに出される地元産野菜のほとんどはプロモーションで配られたものだ。
現在、ブータン政府は、種を配るのではなく、自分で好きな種を選べるようにセレクトショップを各州に1つ設置する準備を進めると同時に、農家自身が種を生産・保存できるよう、コミュニティーシードバンクの設立を推進している。
■コミュニティーシードバンク設立(ブータン農業省HP)
http://www.moaf.gov.bt/moaf/?p=1453
と、提唱したのはブータン国王。
私はブータンではGNH Comissionという機関のコンサルタントという位置付けになっている。
ブータン南部のこの町は外国人が珍しいので(私を含め、現在2人だけ)、よく話しかけられる。
もっとも、ほとんどの人は私をブータン人だと思っているので外国人だというと驚かれるのだけど。
GNHのコンサルタントって何するの?と聞かれることが多々ある。
私の専門は有機農業なので、有機農業は国民のGNHにどう影響するか?もし有機農業でGNHが悪くなるとすれば、どうすれば改善できるのか?というテーマで現状調査をしている。
ブータン政府は2020年までにブータン全土をオーガニックの国にするという至高の目標を掲げている。
ブログ読者からのメールの中には次のようなコメントがあった。
・ブータンって、閉鎖社会でもともと持続的なオーガニックなのでは?
・農薬や化学肥料は輸入しなくてはいけないので裕福な農家しか買えないのでは?
実は低いブータンの食糧自給率
ブータンは、経済のほとんどを海外に依存している。
税金収入は国家収益の1/3。残りは、海外からの援助(おもにインド)と水力発電で賄っている。
コメの自給率は50%。日本より低いのだ。
マーケットに売られている野菜はほとんどがインド産。
地元産は、収穫の季節に自分たちが食べる以上に採れた時のみ売られるため、不定期で価格変動が激しい。
地元産が食べたくなったら農家から直接買うか分けてもらわないといけない。
ブータン人の政府依存体質
ブータン人は、野菜の種や果樹の苗の配給、家畜の医療費、子供の教育まですべて政府に依存している。
農業普及員と村周りしていると、次はこの種がほしい、殺虫剤がほしいとおねだりに出くわす。
自分で買う必要がないので(化学肥料と殺虫剤は低額で配給)、インド人農家のようにわざわざ品種改良に自ら投資したり、雨水集積のための努力をすることはあまりない。
農業普及員はいう。
「農家は有機農業でもっとお金を儲けるためにマーケティングを政府にお願いしてくるのだけど、収量を上げるとか、品質を良くするとか、マーケティング以前に取り組まないといけない努力をせずに結果だけ求めるので困っている。」
ブータン人の海外依存と政府依存は簡単に変えられない困った問題だと思う。
借金漬けになって自殺する農家が後をたたないインドとは違って、土地を含め必要物資はほとんど無料で供給されるブータンはかなり幸せなことだろう。
しかし、農家の自助努力を促す取り組みが必要なのではないだろうか。
農家の自立を促す取り組み
種を大量生産しているのはDruk Seedのみであり、毎年政府が農家からの要望を取りまとめ、Druk Seedに依頼し、各農家に格安で配布されている。
新しい品種などはプロモーションのため無料で配られるため、マーケットに売りに出される地元産野菜のほとんどはプロモーションで配られたものだ。
現在、ブータン政府は、種を配るのではなく、自分で好きな種を選べるようにセレクトショップを各州に1つ設置する準備を進めると同時に、農家自身が種を生産・保存できるよう、コミュニティーシードバンクの設立を推進している。
■コミュニティーシードバンク設立(ブータン農業省HP)
http://www.moaf.gov.bt/moaf/?p=1453
ブータンフィールド便り
ブータンに来て3日がたちました。
ブータン南部の町、Dewathangという町に滞在してます。これからこの町を拠点に南部の村をまわる予定です。ブータンフィールド便り「Go Organic@Bhutan」で村の様子をレポートしていきます。
この度、さっそく第1号を発行しました。主にブータン人有機農家たちのインドでの研修について書いています。
「Go Organic@Bhutan」第1号(英語)

内容:
・世界一幸せな国、ブータンは世界初の有機農業国になれるのか?
・24人のブータン人先進農家が北インドで有機農業トレーニング
・ヒマラヤの村落開発視察旅行
・有機農業のグループ認証システム
・ブータン人農家へのインタビュー
ダウンロードはこちらからお願いします。
日本語の希望者があればどこかで翻訳するかもしれませんが、オランダの読者向けのため今のところニュースレターは英文のみの予定です。
ブータン南部の町、Dewathangという町に滞在してます。これからこの町を拠点に南部の村をまわる予定です。ブータンフィールド便り「Go Organic@Bhutan」で村の様子をレポートしていきます。
この度、さっそく第1号を発行しました。主にブータン人有機農家たちのインドでの研修について書いています。
「Go Organic@Bhutan」第1号(英語)
内容:
・世界一幸せな国、ブータンは世界初の有機農業国になれるのか?
・24人のブータン人先進農家が北インドで有機農業トレーニング
・ヒマラヤの村落開発視察旅行
・有機農業のグループ認証システム
・ブータン人農家へのインタビュー
ダウンロードはこちらからお願いします。
日本語の希望者があればどこかで翻訳するかもしれませんが、オランダの読者向けのため今のところニュースレターは英文のみの予定です。
地獄の36時間列車の耐久レース
ブータン人たちとの旅は楽しいけれど、移動が多すぎて本当に億劫だ。
キレイな水と自然に慣れているブー人にも、汚いインドでの強行旅行はキツイ様子で病人続出だ。
旅のクライマックスは、デリーからアッサム州グワハティに向かう列車だ。AC(エアコン)車を取る予算がなかったため、スリーパークラスの一番下、一番スローな電車にのるはめになった。
君は差額を自腹で払うならAC車両に換えてもいいよ、と言われたけれど、2日半も一人でAC車にいても暇だろうと思い、ブータン人たちと一緒に残った。
デリー駅夜11時発。2泊3日、最後の旅の始まりだった。

夜のニューデリー駅はごった返していた。電車が到着するや否や、乗客はドアが開く前に次々と窓から乗り込んだ。スリーパークラスは座席指定にもかかわらず、どんどん押しかけてくる。気を抜けば座る場所がなくなっている。そして、どうやって乗ったのか次々と物乞いが来て、時にタンバリンで歌いはじめる。女装したオカマがブータン人の頬を叩き、お金を要求する。聞きしに勝る光景だった。
1日目はまだこの状況を楽しむ余裕があった。朝、列車は一気に冷え込んだ。毛布は持ってきていない。着れるだけの服を着て、バスタオルをかぶるもまだ寒い。寒さに耐えながら朝を待つ。
やっとうつらうつらしてきたころ、朝5時。強制チャイで目を覚ます。
「チャイ!チャイ!チャイ!」と、大声で係員が売り歩く。ほんと放っておいてくれない国だ。
朝になると、乗客は一気に増えた。ベッドには所狭しと切符をもっていない乗客が座り込む。彼らは座席を買う余裕がなく、子供を抱えた女性を追い出すことはできない。ベッドに座れない乗客は床に座り込み、身動きがとれないほどだった。
そんな中、日中は40度を越えるであろう熱風が襲った。扇風機の風はむなしく熱風を送るのみ。売られているミネラルウォーターは、もはやお湯だった。車内食は食べられたものじゃなかった。めまいと吐き気がした。これは何かの罰ゲームなのか。
この状態が2日も続くのか・・・。果てしない試練のような気がした。差額を払ってACに移りたい気持ちに駆られたが、それは同じく耐えているブー仲間たちへの裏切りのように思えた。
「おお、神よ、サウナのような列車で2日間過ごすことをお許しになり感謝します。」
朦朧とする意識の中でそう唱えるのが精一杯だった。
しかし、ブータン人たちは、押し寄せるインド人との会話を楽しんでいるようだった。時にジョークを言いながら、食べ物を分け合い、友好関係を築き、おかげで夜は穏便に寝ることができた。こういうことができるのはほんとにすごいと思う。
プライバシー観念の強い日本で過ごしていると、インド人のしつこさをウザイと感じ、放っておいてほしいと思ってしまう。あえて数日ばかりの友好関係を築く気にはなれなかったのだ。彼らからは多くのことを学んだ。
日本に帰ったらこのウザさ加減が懐かしく思うかもしれない。
キレイな水と自然に慣れているブー人にも、汚いインドでの強行旅行はキツイ様子で病人続出だ。
旅のクライマックスは、デリーからアッサム州グワハティに向かう列車だ。AC(エアコン)車を取る予算がなかったため、スリーパークラスの一番下、一番スローな電車にのるはめになった。
君は差額を自腹で払うならAC車両に換えてもいいよ、と言われたけれど、2日半も一人でAC車にいても暇だろうと思い、ブータン人たちと一緒に残った。
デリー駅夜11時発。2泊3日、最後の旅の始まりだった。
夜のニューデリー駅はごった返していた。電車が到着するや否や、乗客はドアが開く前に次々と窓から乗り込んだ。スリーパークラスは座席指定にもかかわらず、どんどん押しかけてくる。気を抜けば座る場所がなくなっている。そして、どうやって乗ったのか次々と物乞いが来て、時にタンバリンで歌いはじめる。女装したオカマがブータン人の頬を叩き、お金を要求する。聞きしに勝る光景だった。
1日目はまだこの状況を楽しむ余裕があった。朝、列車は一気に冷え込んだ。毛布は持ってきていない。着れるだけの服を着て、バスタオルをかぶるもまだ寒い。寒さに耐えながら朝を待つ。
やっとうつらうつらしてきたころ、朝5時。強制チャイで目を覚ます。
「チャイ!チャイ!チャイ!」と、大声で係員が売り歩く。ほんと放っておいてくれない国だ。
朝になると、乗客は一気に増えた。ベッドには所狭しと切符をもっていない乗客が座り込む。彼らは座席を買う余裕がなく、子供を抱えた女性を追い出すことはできない。ベッドに座れない乗客は床に座り込み、身動きがとれないほどだった。
そんな中、日中は40度を越えるであろう熱風が襲った。扇風機の風はむなしく熱風を送るのみ。売られているミネラルウォーターは、もはやお湯だった。車内食は食べられたものじゃなかった。めまいと吐き気がした。これは何かの罰ゲームなのか。
この状態が2日も続くのか・・・。果てしない試練のような気がした。差額を払ってACに移りたい気持ちに駆られたが、それは同じく耐えているブー仲間たちへの裏切りのように思えた。
「おお、神よ、サウナのような列車で2日間過ごすことをお許しになり感謝します。」
朦朧とする意識の中でそう唱えるのが精一杯だった。
しかし、ブータン人たちは、押し寄せるインド人との会話を楽しんでいるようだった。時にジョークを言いながら、食べ物を分け合い、友好関係を築き、おかげで夜は穏便に寝ることができた。こういうことができるのはほんとにすごいと思う。
プライバシー観念の強い日本で過ごしていると、インド人のしつこさをウザイと感じ、放っておいてほしいと思ってしまう。あえて数日ばかりの友好関係を築く気にはなれなかったのだ。彼らからは多くのことを学んだ。
日本に帰ったらこのウザさ加減が懐かしく思うかもしれない。
ヒマラヤのオーガニックビジネス
ブー人御一行はバスで丸一日かけ、ガンジス川の源流に位置する村、Raniketへ向かう。ヒマラヤの麓のこの村では標高差がかなりあるため、取れる野菜も異なる。村同士で野菜の交換を行い、ほぼ自給できている。そこで、PGS(Participatory Gurantee System)という、グループでオーガニック認証を保障しあうという手法を学んだ。
Ranikhetの生活向上支援を行う地元のNGO、"Grassroots"は、森林保全、エネルギーの自活、マイクロクレジット、コミュニティビジネスなどの活動を行っている。

オーガニックのグループ認証を行うにあたっては、しっかりと組織されたグループがキーとなる。オーガニック認証会社などの第三者による認証が広く受け入れられているやり方であるが、視察などの手数料は小規模農家にとってはかなりの負担となる。グループ認証では、グループ内のメンバーが自発的にお互いの農業を監視することで、オーガニックであることを保障するため、認証にかかる手数料が発生しない。
年一度の視察では、消費者やPGS協会などのメンバーが化学肥料や農薬が使われていないかチェックする。PGSにおいては、第三者認証を受けない代わりに、農家、消費者、NGO、コミュニティ全体でオーガニックを認め合うのだ。
以前の記事で書いたがインドでは、SHG(self help group)という女性のグループを作る運動が盛んで、共同預金や、グループ間でのお金の貸し借り、コミュニティビジネスのための共同投資などが行われている。この地区のオーガニック認証においてもSHGを基本としてグループ認証を受けていた。この地区にある52のSHGのうち、48はすでにオーガニック認証を取得している。かなり有機農業比率が高い。
16のSHGの代表から組織されるVillage Development Council (村落開発協会)の代表理事によると、最初はオーガニックに転換することをためらう農家が多く、一年目は十分な収量が得られなかったという。しかし、2年目には、ほぼ慣行農法の頃に近い収量を得ることができ、3年めにはオーガニックマーケティングを行う会社との契約により全国に出荷できることになった。
Grassrootsは、「Umang」というブランドのコミュニティビジネス会社を立ち上げた。
「私たちは、彼らがもともと持っている知識に自身を与えただけ」と、NGOスタッフは言う。
ほとんどの家庭が持っているバイオガス発電設備やダムの改修、パッケージング機械を購入する費用のほとんどは、農家自身が負担している。政府の補助金を代わりに申請することはしても、NGOとして資金の支援はしていないという。
「女性は、男性に比べてお金の管理がうまく、ビジネスセンスが高い。」
なぜ、女性だけのグループで男性は参加しないのか尋ねると、村の男性はお金があるとすぐにギャンブルやお酒に使ってしまうのだとか。
思い当たるふしがあるのか、ブータン人の男性たちはだまっていた・・・。
ちなみに、オーガニックのグループ認証は、インドなどの途上国ばかりでなく、アメリカ、ニュージーランドなどの先進国でも用いられている。日本でグループ認証を行っているところはあるのだろうか?PGSで検索しても日本語ではあまりでてこなかった。ともかく一部であったとしてもあまり盛んではないようだ。ブータンではこれから導入を予定しているそうだ。
日本人には有機認証取得にかかる費用はそれほど大きな負担ではないのだろうか。それとも制度そのものがまだ整っていないのだろうか?帰国したら調べてみたい。

(写真:ホームステイ先で)
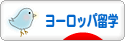

Ranikhetの生活向上支援を行う地元のNGO、"Grassroots"は、森林保全、エネルギーの自活、マイクロクレジット、コミュニティビジネスなどの活動を行っている。
オーガニックのグループ認証を行うにあたっては、しっかりと組織されたグループがキーとなる。オーガニック認証会社などの第三者による認証が広く受け入れられているやり方であるが、視察などの手数料は小規模農家にとってはかなりの負担となる。グループ認証では、グループ内のメンバーが自発的にお互いの農業を監視することで、オーガニックであることを保障するため、認証にかかる手数料が発生しない。
年一度の視察では、消費者やPGS協会などのメンバーが化学肥料や農薬が使われていないかチェックする。PGSにおいては、第三者認証を受けない代わりに、農家、消費者、NGO、コミュニティ全体でオーガニックを認め合うのだ。
以前の記事で書いたがインドでは、SHG(self help group)という女性のグループを作る運動が盛んで、共同預金や、グループ間でのお金の貸し借り、コミュニティビジネスのための共同投資などが行われている。この地区のオーガニック認証においてもSHGを基本としてグループ認証を受けていた。この地区にある52のSHGのうち、48はすでにオーガニック認証を取得している。かなり有機農業比率が高い。
16のSHGの代表から組織されるVillage Development Council (村落開発協会)の代表理事によると、最初はオーガニックに転換することをためらう農家が多く、一年目は十分な収量が得られなかったという。しかし、2年目には、ほぼ慣行農法の頃に近い収量を得ることができ、3年めにはオーガニックマーケティングを行う会社との契約により全国に出荷できることになった。
Grassrootsは、「Umang」というブランドのコミュニティビジネス会社を立ち上げた。
「私たちは、彼らがもともと持っている知識に自身を与えただけ」と、NGOスタッフは言う。
ほとんどの家庭が持っているバイオガス発電設備やダムの改修、パッケージング機械を購入する費用のほとんどは、農家自身が負担している。政府の補助金を代わりに申請することはしても、NGOとして資金の支援はしていないという。
「女性は、男性に比べてお金の管理がうまく、ビジネスセンスが高い。」
なぜ、女性だけのグループで男性は参加しないのか尋ねると、村の男性はお金があるとすぐにギャンブルやお酒に使ってしまうのだとか。
思い当たるふしがあるのか、ブータン人の男性たちはだまっていた・・・。
ちなみに、オーガニックのグループ認証は、インドなどの途上国ばかりでなく、アメリカ、ニュージーランドなどの先進国でも用いられている。日本でグループ認証を行っているところはあるのだろうか?PGSで検索しても日本語ではあまりでてこなかった。ともかく一部であったとしてもあまり盛んではないようだ。ブータンではこれから導入を予定しているそうだ。
日本人には有機認証取得にかかる費用はそれほど大きな負担ではないのだろうか。それとも制度そのものがまだ整っていないのだろうか?帰国したら調べてみたい。
(写真:ホームステイ先で)
なぜ旅をするのか?
「君は何をしているのか?」
24人のブータン人御一向を率いる団長は、インドで一人旅している日本人女性を不思議に思いたずねた。その女性は英語がまったく話せなかったので私が通訳をした。
女性「一人旅をしている」
ブー団長「何のために旅をしているのか」
女性「・・・」
ブー団長「何が目的なのか?たとえば、私たちは農業のトレーニングのためにインドに来た。ここにいるみけは、研究のために来ている。君は何がしたいのか?」
女性はうまく答えられないようだった。
ブー団長「なぜ英語が話せないのか?勉強しないのか?」
団長はさらに質問を続けるが彼女は黙る。これから英語を勉強すると言うのが精一杯だった。
ブー団長「Are you STUPID?」
君はバカなのか?と、言ってるよ、と直訳させてもらった。
この質問には女性はびっくりしていた。
ブー団長「もし、君が僕の家族なら殴っているところだ」
さすがにこれは訳さなかった^^;
目的なくただ旅をしている女性を、ブー団長には全く理解できないようだった。
そもそも、ブータンには一人旅をする人はいない。というか、誰かに会うためにほかの町に出かける以外、旅する理由がなければ、観光施設もないのだ。他の町に行く時は親族の家か友達の家に泊まる。
オランダにいた頃も、ブータン人はいつも一緒にご飯を食べていた。一人暮らしできず、必ず相部屋で生活していた。一人暮らしなんて、寂しくてできないという。
日本では結婚もせずに家族と暮らしていれば「パラサイトシングル」と呼ばれる。これを言うと、ブータン人には何が悪いのかわからない。逆に、なぜ一人で暮らすのかと聞かれる。
ある日、トレーニングの空き時間に数人でバザールに出かけた。
置いてけぼりを食った女性(20代)は、「友達だと思ってたのに置いていくなんて!」と、一晩中泣き、次の日もベッドにもぐりこんでしまっていた。バザールに行った仲間は次々に彼女のお見舞い?に訪れてなぐさめた。
小学生じゃないんだからそのくらいのことで・・・とあきれたのだけど、これも集団生活を重んじるブータン人ならではなのかもしれない。
とにかく、一人旅なんて彼らにとっては論外なのだ。
さらに、目的のない旅、つまり「旅そのものが目的」という理屈がわからない。

「日本人はお金持ちだからそんな浪費ができるんだね。そんなお金があったらもっと社会の役に立つことができるだろうに。」
と、ブータン人。これには返す言葉もない。
自分も昔は目的なくただ旅を楽しんでいたので何ともいえない。1都市にせいぜい1週間滞在しては満足して移動を繰り返していた。そして訪れた国数を数え、パスポートのスタンプを眺めていた。その時間があればもっと学べることがあったはずなのに。今は何をしていたのか聞かれるのが嫌で、あえて言わないことにしている。
何もしなくても生きていけることは、最高の贅沢だ。それを自覚せずに、もらっているものの上にあぐらをかいていればSTUPIDと言われても仕方ないだろう。
自分に言われているような気がした。私はもらっているものに対し何を返せるだろうか?
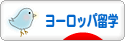

24人のブータン人御一向を率いる団長は、インドで一人旅している日本人女性を不思議に思いたずねた。その女性は英語がまったく話せなかったので私が通訳をした。
女性「一人旅をしている」
ブー団長「何のために旅をしているのか」
女性「・・・」
ブー団長「何が目的なのか?たとえば、私たちは農業のトレーニングのためにインドに来た。ここにいるみけは、研究のために来ている。君は何がしたいのか?」
女性はうまく答えられないようだった。
ブー団長「なぜ英語が話せないのか?勉強しないのか?」
団長はさらに質問を続けるが彼女は黙る。これから英語を勉強すると言うのが精一杯だった。
ブー団長「Are you STUPID?」
君はバカなのか?と、言ってるよ、と直訳させてもらった。
この質問には女性はびっくりしていた。
ブー団長「もし、君が僕の家族なら殴っているところだ」
さすがにこれは訳さなかった^^;
目的なくただ旅をしている女性を、ブー団長には全く理解できないようだった。
そもそも、ブータンには一人旅をする人はいない。というか、誰かに会うためにほかの町に出かける以外、旅する理由がなければ、観光施設もないのだ。他の町に行く時は親族の家か友達の家に泊まる。
オランダにいた頃も、ブータン人はいつも一緒にご飯を食べていた。一人暮らしできず、必ず相部屋で生活していた。一人暮らしなんて、寂しくてできないという。
日本では結婚もせずに家族と暮らしていれば「パラサイトシングル」と呼ばれる。これを言うと、ブータン人には何が悪いのかわからない。逆に、なぜ一人で暮らすのかと聞かれる。
ある日、トレーニングの空き時間に数人でバザールに出かけた。
置いてけぼりを食った女性(20代)は、「友達だと思ってたのに置いていくなんて!」と、一晩中泣き、次の日もベッドにもぐりこんでしまっていた。バザールに行った仲間は次々に彼女のお見舞い?に訪れてなぐさめた。
小学生じゃないんだからそのくらいのことで・・・とあきれたのだけど、これも集団生活を重んじるブータン人ならではなのかもしれない。
とにかく、一人旅なんて彼らにとっては論外なのだ。
さらに、目的のない旅、つまり「旅そのものが目的」という理屈がわからない。
「日本人はお金持ちだからそんな浪費ができるんだね。そんなお金があったらもっと社会の役に立つことができるだろうに。」
と、ブータン人。これには返す言葉もない。
自分も昔は目的なくただ旅を楽しんでいたので何ともいえない。1都市にせいぜい1週間滞在しては満足して移動を繰り返していた。そして訪れた国数を数え、パスポートのスタンプを眺めていた。その時間があればもっと学べることがあったはずなのに。今は何をしていたのか聞かれるのが嫌で、あえて言わないことにしている。
何もしなくても生きていけることは、最高の贅沢だ。それを自覚せずに、もらっているものの上にあぐらをかいていればSTUPIDと言われても仕方ないだろう。
自分に言われているような気がした。私はもらっているものに対し何を返せるだろうか?
プロフィール
ブログ移動しました
「アグロエコロジー」続編:
http://agro-ecology.blogspot.jp/
たねのもりびと
ワーゲニンゲン大学大学院
有機農業研究科修了
(アグロエコロジー専攻)
Wageningen University
MSc of Organic Agriculture
ブータン政府GNH委員会インターン
国を100%オーガニックにする国家プロジェクトに従事
■ご挨拶
ご挨拶
■連絡先
メールフォーム
当サイトはリンクフリーです。

「アグロエコロジー」続編:
http://agro-ecology.blogspot.jp/
たねのもりびと
ワーゲニンゲン大学大学院
有機農業研究科修了
(アグロエコロジー専攻)
Wageningen University
MSc of Organic Agriculture
ブータン政府GNH委員会インターン
国を100%オーガニックにする国家プロジェクトに従事
■ご挨拶
ご挨拶
■連絡先
メールフォーム
当サイトはリンクフリーです。

